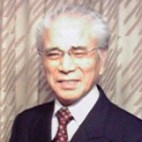福井新聞 Online 論説/勝山の西脇呉石展
2019年8月7日 就職・転職日 本 生 涯 現 役 推 進 協 議 会 &
NPO法人 ラ イ フ ・ ベ ン チ ャ ー ・ ク ラ ブ 活 動 で
ご 支 援 く だ さ る 会 員 皆 様
福井新聞 Online HOME 論説 2019年8月7日 午前7時30分
ご参考URL=https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/909982
勝山の西脇呉石展 伝統の書、極めた生涯に光
【論説】勝山市生まれの書家に西脇呉石(ごせき)(1879~1970年)がいる。大正期に多数の書道教科書を揮毫(きごう)し、戦前の書道教育分野で名高いが地元福井での認知度は必ずしも高くない。勝山城博物館で開かれている特別展「福井の偉人 書家西脇呉石~研ぎ澄まされた心と線」(~9月30日)は書作品を中心に詩稿、印などが披露され、呉石の業績を体系立てて知ることができる。
2013年以降、同館には遺族から作品や資料など数百点が寄付・寄託され、日本近代書道史が専門の林淳学芸員が整理・調査。生誕140年を記念して勝山市と特別展を企画した。
旧越前勝山藩士西脇糺の子として生まれた呉石は、明治32(1899)年に福井県師範学校を卒業。同年、西日本の教科書揮毫の第一人者だった書家村田海石に入門した。同40年、東京府師範学校教諭となり、「明治の三筆」に数えられる日下部鳴鶴(くさかべめいかく)に師事した。昭和初期には、国内最大の書道団体「泰東書道院」理事となり、書家としての地歩を固めた。
教科書や手本の揮毫・編集に携わったのは明治30年代からで、著作は100冊以上。大正期に全国の小学校で使われた国定教科書も手掛けた。
戦後は一般向けの文化書道会(東京)を立ち上げ、「実用の書家」というイメージが強いが、最晩年まで無鑑査の立場で日展や毎日書道展に「芸術の書」を発表し活躍。特別展では両展覧会に出品した12点を中心に据える。ほとんどが自作の漢詩が題材で、70代から最晩年までの作品を年代順に追うことで、無為自然に変化する「芸術性の進化」が確認できる。
林学芸員によれば、呉石が70代を迎えた1950年代初頭、作家の内面の感覚を熱く激しく表出するような抽象表現美術「アンフォルメル」が欧米で登場し、やがて日本の書壇にも影響を及ぼした。「前衛書にこそ芸術性がある」との考えが潮流となる中で、呉石は「磨き上げた技術の上に自然とにじみ出てくるものこそが個性」と考え、あえて「創り上げる」ことをしなかった。それが「前近代的」ととらえられ、歴史に埋没したと推察される。
価値観が大転換した書壇と一線を画し、呉石は日本の伝統的な芸術観を根底に据え、自己の目指す書を世に問い続けた。人格の修養と国語や漢文に習熟した広い教養から生み出された作品は、能楽などの伝統芸能の美にも通じる在り方だと林学芸員は解説する。呉石が長寿で生涯現役だったために到達できた世界でもある。2020年は呉石の没後50年にあたる。特別展を契機に、呉石の作品と芸術観を見つめ直し、勝山の偉人として未来に伝えたい。
NPO法人 ラ イ フ ・ ベ ン チ ャ ー ・ ク ラ ブ 活 動 で
ご 支 援 く だ さ る 会 員 皆 様
福井新聞 Online HOME 論説 2019年8月7日 午前7時30分
ご参考URL=https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/909982
勝山の西脇呉石展 伝統の書、極めた生涯に光
【論説】勝山市生まれの書家に西脇呉石(ごせき)(1879~1970年)がいる。大正期に多数の書道教科書を揮毫(きごう)し、戦前の書道教育分野で名高いが地元福井での認知度は必ずしも高くない。勝山城博物館で開かれている特別展「福井の偉人 書家西脇呉石~研ぎ澄まされた心と線」(~9月30日)は書作品を中心に詩稿、印などが披露され、呉石の業績を体系立てて知ることができる。
2013年以降、同館には遺族から作品や資料など数百点が寄付・寄託され、日本近代書道史が専門の林淳学芸員が整理・調査。生誕140年を記念して勝山市と特別展を企画した。
旧越前勝山藩士西脇糺の子として生まれた呉石は、明治32(1899)年に福井県師範学校を卒業。同年、西日本の教科書揮毫の第一人者だった書家村田海石に入門した。同40年、東京府師範学校教諭となり、「明治の三筆」に数えられる日下部鳴鶴(くさかべめいかく)に師事した。昭和初期には、国内最大の書道団体「泰東書道院」理事となり、書家としての地歩を固めた。
教科書や手本の揮毫・編集に携わったのは明治30年代からで、著作は100冊以上。大正期に全国の小学校で使われた国定教科書も手掛けた。
戦後は一般向けの文化書道会(東京)を立ち上げ、「実用の書家」というイメージが強いが、最晩年まで無鑑査の立場で日展や毎日書道展に「芸術の書」を発表し活躍。特別展では両展覧会に出品した12点を中心に据える。ほとんどが自作の漢詩が題材で、70代から最晩年までの作品を年代順に追うことで、無為自然に変化する「芸術性の進化」が確認できる。
林学芸員によれば、呉石が70代を迎えた1950年代初頭、作家の内面の感覚を熱く激しく表出するような抽象表現美術「アンフォルメル」が欧米で登場し、やがて日本の書壇にも影響を及ぼした。「前衛書にこそ芸術性がある」との考えが潮流となる中で、呉石は「磨き上げた技術の上に自然とにじみ出てくるものこそが個性」と考え、あえて「創り上げる」ことをしなかった。それが「前近代的」ととらえられ、歴史に埋没したと推察される。
価値観が大転換した書壇と一線を画し、呉石は日本の伝統的な芸術観を根底に据え、自己の目指す書を世に問い続けた。人格の修養と国語や漢文に習熟した広い教養から生み出された作品は、能楽などの伝統芸能の美にも通じる在り方だと林学芸員は解説する。呉石が長寿で生涯現役だったために到達できた世界でもある。2020年は呉石の没後50年にあたる。特別展を契機に、呉石の作品と芸術観を見つめ直し、勝山の偉人として未来に伝えたい。
加藤特許事務所:知財とびうめ便り44号
2015年9月1日 就職・転職◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
「加藤特許事務所 ~知財 とびうめ便り~」 Vol.44
発信日:2015年 9月 1日 発信者:加藤特許事務所
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
★ 目 次 ★
1.弁理士コラム
●知財を取り巻く環境の変化について
2.知財ニュース
●特許庁、新たな外国特許情報サービス「FOPISER」を開始
3.連載 知財講座
●第44回:特許「国内優先出願」
4.イベント案内
●平成27年度実務者向け知的財産権制度説明会開催
5.事務所からのお知らせ
●特許庁の中小企業向け支援策の紹介
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.弁理士コラム
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●知財を取り巻く環境の変化について
私が、知的財産の業界に入って今年で8年目になりますが、特に近年、知的財産を取り巻く環境はダイナミックに変化しており、数年前の常識は既に通用しなくなっていると強く感じています。
特許法1条に「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする」とされているように、特許法の目的はあくまでも「(日本国内の)産業の発達」であり、発明の保護及び利用を制度として定めた産業振興法といえます。そのため、産業振興施策として、その時々の社会状況に応じて特許庁自体の運用自体が変わることも起こり得ます。
一例を挙げますと、製造方法で特定した物の発明(プロダクトバイプロセスクレーム)について、これまでの特許庁の審査運用を半ば否定する最高裁判決が出され、特許庁の審査基準自体の改定を迫られています(現在は暫定審査基準での運用)。
また、本年度と昨年度の「特許出願件数」と「特許登録件数」について、特許庁の統計データを確認したところ、6月末時点(1月~6月まで)での特許出願件数は、本年、昨年ともに約16万件で、ほぼ変わりありませんが、特許登録件数は、6月末時点で約9万7千件と昨年同期より約22%(約2万1千件)も減少していました。
もちろん単純な数字のみで比較できない面もありますが、実務担当としても本年度に入り特許審査が以前より厳しくなったと感じており、特許庁が、審査をより厳格に行う運用になったこと自体は間違いないと判断しています。
なお、この理由としては、推測になりますが、FA11(特許審査待ち期間を11か月以内)を達成するために審査自体が若干甘くなっていたことへの反動や、特許異議申立制度が復活したこと等の影響と考えています。
このように特許庁の運用自体も時代と共に変化していますし、来年以降も職務発明制度の改定、特許法条約(PLT)への加盟等、知的財産を取り巻く環境はさらにダイナミックに変化していくようです。
弊所ではこのような変化を十分に踏まえ、皆様方の知的財産権の取得のみならず、その活用について的確にアドバイスできるよう日々研鑽を続けていきます。
弁理士 森 博
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.知財ニュース
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●特許庁、新たな外国特許情報サービス「FOPISER」を開始
特許庁は、新たな外国特許情報の照会サービス「FOPISER(フォピサー)」を、本年8月7日より開始しました。
このフォピサーは、すでに特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」で提供されている欧米・中国・韓国等の諸外国以外の特許情報への照会を、日本語のインターフェースを通じて無料で行うことを可能とするもので、サービス開始当初においては、ロシア・台湾・オーストラリアの特許・実用新案文献、及びロシア・台湾の意匠文献を照会することができます。
照会可能な外国特許情報については、順次拡大を図り、次はフィリピン、シンガポール等の特許情報の掲載を予定しています。
システムの詳細は、下記のPDFをご参照ください。
[URL] http://www.meti.go.jp/press/2015/08/20150806001/20150806001.pdf
「フォピサー」へリンクはこちら。
[URL] https://www.foreignsearch.jpo.go.jp/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.連載 知財講座
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
第44回:特許「国内優先出願」
国内優先出願は、特許法第41条に規定される、特許出願等に基づく優先権(国内優先権)を主張した特許出願です。
「優先権」とは、パリ条約において規定された概念であり、いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願をすることに関し、1年間の優先権を有するという制度ですが、この制度を、日本国内の後の出願においても適用するというのが国内優先権の趣旨です。
本制度により、先の基本的な発明の出願の後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願を行うことができ、技術開発の成果が漏れのない形で円滑に特許権として保護されることが容易になります。
国内優先権を主張できる者は、先の出願の出願人です。したがって、先の出願の出願人と後の出願との出願人とが、後の出願の時点において同一であることが必要です。
国内優先権の主張ができる期間は原則として先の出願の日から1年です。国内優先出願の利用形態として、次に掲げる(1)~(4)が考えられます。
(1)実施形態の補充型:先の出願に記載した実施形態が説明不足なので補足した場合や、先の出願の発明に含まれる別の実施形態を追加して確実に権利化を図りたい場合
(2)改良発明追加型:先の出願に記載した発明に基づいて考えられた改良発明を追加したい場合
(3)出願併合型:すでに出願済みの例えば2つの発明を1つにまとめて出願したい場合(但し、発明の単一性を満たすこと)
(4)上位概念抽出型:すでに出願済みの例えば2つの発明をまとめて、両発明を包含する上位概念としての発明として出願したい場合
但し、先の出願が、すでに放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合等においては、国内優先権を主張して出願することはできません。
なお、特許要件(新規性、進歩性等)の判断は、国内優先出願に係る発明のうち、先の出願の明細書に記載されている発明については、先の出願の出願日が基準となります。
また、国内優先が認められた出願についての出願審査請求期間及び特許権の存続期間の起算日は、当該後の出願の出願日となります。
以上のように国内優先権に基づく出願は、すでに出願済み(先の出願)の発明に対して、実施形態の追加や改良発明・拡張発明を取り込んだ包括的な出願を行うことができますので、発明の質の向上が図れ、ひいては強い特許を取得することに結びつきます。
皆さま、ぜひこの国内優先出願の制度をご活用ください。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4.イベント案内
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
● 平成27年度実務者向け知的財産権制度説明会開催
特許庁は、知的財産権の業務に携わっている実務者の方を対象に、制度の円滑な運用を図るため、実務上必要な知識の習得を目的とした実務者向け説明会を全国の主要都市で開催します。
本説明会では特許・意匠・商標の審査基準やその運用、審判制度の運用等について、特許庁職員が解説します。参加の場合は、事前申込が必要で、参加は無料です。九州・沖縄での開催日は、次の通りです。
福岡市:11/16,12/3,12/14,12/21、熊本市:10/1,12/9、鹿児島市:12/15、那覇市:11/9
詳細は、下記のURLをご覧ください。
[URL] http://www.jiii.or.jp/h27_jitsumusya/index.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
5.事務所からのお知らせ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●特許庁の中小企業向け支援策の紹介
特許庁が実施している中小企業向け5つの支援策(審査請求料・特許料軽減制度、外国出願補助金等)について、特許庁は「中小企業と知財を"つなぐ"支援策」というタイトルで動画配信中です。
下記のURLより、動画をご覧いただけます。
[URL] https://www.youtube.com/watch?v=rS4arIZYZt8&feature=youtu.be
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
加藤特許事務所
編集・発行: 加藤特許事務所 -メルマガ事務局-
福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号 博多駅前ビジネスセンター411号
URL:http://www.kato-pat.jp/
TEL:092-413-5378 E-mail:mail@kato-pat.jp
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
「加藤特許事務所 ~知財 とびうめ便り~」 Vol.44
発信日:2015年 9月 1日 発信者:加藤特許事務所
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
★ 目 次 ★
1.弁理士コラム
●知財を取り巻く環境の変化について
2.知財ニュース
●特許庁、新たな外国特許情報サービス「FOPISER」を開始
3.連載 知財講座
●第44回:特許「国内優先出願」
4.イベント案内
●平成27年度実務者向け知的財産権制度説明会開催
5.事務所からのお知らせ
●特許庁の中小企業向け支援策の紹介
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.弁理士コラム
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●知財を取り巻く環境の変化について
私が、知的財産の業界に入って今年で8年目になりますが、特に近年、知的財産を取り巻く環境はダイナミックに変化しており、数年前の常識は既に通用しなくなっていると強く感じています。
特許法1条に「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする」とされているように、特許法の目的はあくまでも「(日本国内の)産業の発達」であり、発明の保護及び利用を制度として定めた産業振興法といえます。そのため、産業振興施策として、その時々の社会状況に応じて特許庁自体の運用自体が変わることも起こり得ます。
一例を挙げますと、製造方法で特定した物の発明(プロダクトバイプロセスクレーム)について、これまでの特許庁の審査運用を半ば否定する最高裁判決が出され、特許庁の審査基準自体の改定を迫られています(現在は暫定審査基準での運用)。
また、本年度と昨年度の「特許出願件数」と「特許登録件数」について、特許庁の統計データを確認したところ、6月末時点(1月~6月まで)での特許出願件数は、本年、昨年ともに約16万件で、ほぼ変わりありませんが、特許登録件数は、6月末時点で約9万7千件と昨年同期より約22%(約2万1千件)も減少していました。
もちろん単純な数字のみで比較できない面もありますが、実務担当としても本年度に入り特許審査が以前より厳しくなったと感じており、特許庁が、審査をより厳格に行う運用になったこと自体は間違いないと判断しています。
なお、この理由としては、推測になりますが、FA11(特許審査待ち期間を11か月以内)を達成するために審査自体が若干甘くなっていたことへの反動や、特許異議申立制度が復活したこと等の影響と考えています。
このように特許庁の運用自体も時代と共に変化していますし、来年以降も職務発明制度の改定、特許法条約(PLT)への加盟等、知的財産を取り巻く環境はさらにダイナミックに変化していくようです。
弊所ではこのような変化を十分に踏まえ、皆様方の知的財産権の取得のみならず、その活用について的確にアドバイスできるよう日々研鑽を続けていきます。
弁理士 森 博
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.知財ニュース
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●特許庁、新たな外国特許情報サービス「FOPISER」を開始
特許庁は、新たな外国特許情報の照会サービス「FOPISER(フォピサー)」を、本年8月7日より開始しました。
このフォピサーは、すでに特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」で提供されている欧米・中国・韓国等の諸外国以外の特許情報への照会を、日本語のインターフェースを通じて無料で行うことを可能とするもので、サービス開始当初においては、ロシア・台湾・オーストラリアの特許・実用新案文献、及びロシア・台湾の意匠文献を照会することができます。
照会可能な外国特許情報については、順次拡大を図り、次はフィリピン、シンガポール等の特許情報の掲載を予定しています。
システムの詳細は、下記のPDFをご参照ください。
[URL] http://www.meti.go.jp/press/2015/08/20150806001/20150806001.pdf
「フォピサー」へリンクはこちら。
[URL] https://www.foreignsearch.jpo.go.jp/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.連載 知財講座
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
第44回:特許「国内優先出願」
国内優先出願は、特許法第41条に規定される、特許出願等に基づく優先権(国内優先権)を主張した特許出願です。
「優先権」とは、パリ条約において規定された概念であり、いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願をすることに関し、1年間の優先権を有するという制度ですが、この制度を、日本国内の後の出願においても適用するというのが国内優先権の趣旨です。
本制度により、先の基本的な発明の出願の後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願を行うことができ、技術開発の成果が漏れのない形で円滑に特許権として保護されることが容易になります。
国内優先権を主張できる者は、先の出願の出願人です。したがって、先の出願の出願人と後の出願との出願人とが、後の出願の時点において同一であることが必要です。
国内優先権の主張ができる期間は原則として先の出願の日から1年です。国内優先出願の利用形態として、次に掲げる(1)~(4)が考えられます。
(1)実施形態の補充型:先の出願に記載した実施形態が説明不足なので補足した場合や、先の出願の発明に含まれる別の実施形態を追加して確実に権利化を図りたい場合
(2)改良発明追加型:先の出願に記載した発明に基づいて考えられた改良発明を追加したい場合
(3)出願併合型:すでに出願済みの例えば2つの発明を1つにまとめて出願したい場合(但し、発明の単一性を満たすこと)
(4)上位概念抽出型:すでに出願済みの例えば2つの発明をまとめて、両発明を包含する上位概念としての発明として出願したい場合
但し、先の出願が、すでに放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合等においては、国内優先権を主張して出願することはできません。
なお、特許要件(新規性、進歩性等)の判断は、国内優先出願に係る発明のうち、先の出願の明細書に記載されている発明については、先の出願の出願日が基準となります。
また、国内優先が認められた出願についての出願審査請求期間及び特許権の存続期間の起算日は、当該後の出願の出願日となります。
以上のように国内優先権に基づく出願は、すでに出願済み(先の出願)の発明に対して、実施形態の追加や改良発明・拡張発明を取り込んだ包括的な出願を行うことができますので、発明の質の向上が図れ、ひいては強い特許を取得することに結びつきます。
皆さま、ぜひこの国内優先出願の制度をご活用ください。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4.イベント案内
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
● 平成27年度実務者向け知的財産権制度説明会開催
特許庁は、知的財産権の業務に携わっている実務者の方を対象に、制度の円滑な運用を図るため、実務上必要な知識の習得を目的とした実務者向け説明会を全国の主要都市で開催します。
本説明会では特許・意匠・商標の審査基準やその運用、審判制度の運用等について、特許庁職員が解説します。参加の場合は、事前申込が必要で、参加は無料です。九州・沖縄での開催日は、次の通りです。
福岡市:11/16,12/3,12/14,12/21、熊本市:10/1,12/9、鹿児島市:12/15、那覇市:11/9
詳細は、下記のURLをご覧ください。
[URL] http://www.jiii.or.jp/h27_jitsumusya/index.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
5.事務所からのお知らせ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●特許庁の中小企業向け支援策の紹介
特許庁が実施している中小企業向け5つの支援策(審査請求料・特許料軽減制度、外国出願補助金等)について、特許庁は「中小企業と知財を"つなぐ"支援策」というタイトルで動画配信中です。
下記のURLより、動画をご覧いただけます。
[URL] https://www.youtube.com/watch?v=rS4arIZYZt8&feature=youtu.be
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
加藤特許事務所
編集・発行: 加藤特許事務所 -メルマガ事務局-
福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号 博多駅前ビジネスセンター411号
URL:http://www.kato-pat.jp/
TEL:092-413-5378 E-mail:mail@kato-pat.jp
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆