福井新聞 Online 論説/勝山の西脇呉石展
2019年8月7日 就職・転職日 本 生 涯 現 役 推 進 協 議 会 &
NPO法人 ラ イ フ ・ ベ ン チ ャ ー ・ ク ラ ブ 活 動 で
ご 支 援 く だ さ る 会 員 皆 様
福井新聞 Online HOME 論説 2019年8月7日 午前7時30分
ご参考URL=https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/909982
勝山の西脇呉石展 伝統の書、極めた生涯に光
【論説】勝山市生まれの書家に西脇呉石(ごせき)(1879~1970年)がいる。大正期に多数の書道教科書を揮毫(きごう)し、戦前の書道教育分野で名高いが地元福井での認知度は必ずしも高くない。勝山城博物館で開かれている特別展「福井の偉人 書家西脇呉石~研ぎ澄まされた心と線」(~9月30日)は書作品を中心に詩稿、印などが披露され、呉石の業績を体系立てて知ることができる。
2013年以降、同館には遺族から作品や資料など数百点が寄付・寄託され、日本近代書道史が専門の林淳学芸員が整理・調査。生誕140年を記念して勝山市と特別展を企画した。
旧越前勝山藩士西脇糺の子として生まれた呉石は、明治32(1899)年に福井県師範学校を卒業。同年、西日本の教科書揮毫の第一人者だった書家村田海石に入門した。同40年、東京府師範学校教諭となり、「明治の三筆」に数えられる日下部鳴鶴(くさかべめいかく)に師事した。昭和初期には、国内最大の書道団体「泰東書道院」理事となり、書家としての地歩を固めた。
教科書や手本の揮毫・編集に携わったのは明治30年代からで、著作は100冊以上。大正期に全国の小学校で使われた国定教科書も手掛けた。
戦後は一般向けの文化書道会(東京)を立ち上げ、「実用の書家」というイメージが強いが、最晩年まで無鑑査の立場で日展や毎日書道展に「芸術の書」を発表し活躍。特別展では両展覧会に出品した12点を中心に据える。ほとんどが自作の漢詩が題材で、70代から最晩年までの作品を年代順に追うことで、無為自然に変化する「芸術性の進化」が確認できる。
林学芸員によれば、呉石が70代を迎えた1950年代初頭、作家の内面の感覚を熱く激しく表出するような抽象表現美術「アンフォルメル」が欧米で登場し、やがて日本の書壇にも影響を及ぼした。「前衛書にこそ芸術性がある」との考えが潮流となる中で、呉石は「磨き上げた技術の上に自然とにじみ出てくるものこそが個性」と考え、あえて「創り上げる」ことをしなかった。それが「前近代的」ととらえられ、歴史に埋没したと推察される。
価値観が大転換した書壇と一線を画し、呉石は日本の伝統的な芸術観を根底に据え、自己の目指す書を世に問い続けた。人格の修養と国語や漢文に習熟した広い教養から生み出された作品は、能楽などの伝統芸能の美にも通じる在り方だと林学芸員は解説する。呉石が長寿で生涯現役だったために到達できた世界でもある。2020年は呉石の没後50年にあたる。特別展を契機に、呉石の作品と芸術観を見つめ直し、勝山の偉人として未来に伝えたい。
NPO法人 ラ イ フ ・ ベ ン チ ャ ー ・ ク ラ ブ 活 動 で
ご 支 援 く だ さ る 会 員 皆 様
福井新聞 Online HOME 論説 2019年8月7日 午前7時30分
ご参考URL=https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/909982
勝山の西脇呉石展 伝統の書、極めた生涯に光
【論説】勝山市生まれの書家に西脇呉石(ごせき)(1879~1970年)がいる。大正期に多数の書道教科書を揮毫(きごう)し、戦前の書道教育分野で名高いが地元福井での認知度は必ずしも高くない。勝山城博物館で開かれている特別展「福井の偉人 書家西脇呉石~研ぎ澄まされた心と線」(~9月30日)は書作品を中心に詩稿、印などが披露され、呉石の業績を体系立てて知ることができる。
2013年以降、同館には遺族から作品や資料など数百点が寄付・寄託され、日本近代書道史が専門の林淳学芸員が整理・調査。生誕140年を記念して勝山市と特別展を企画した。
旧越前勝山藩士西脇糺の子として生まれた呉石は、明治32(1899)年に福井県師範学校を卒業。同年、西日本の教科書揮毫の第一人者だった書家村田海石に入門した。同40年、東京府師範学校教諭となり、「明治の三筆」に数えられる日下部鳴鶴(くさかべめいかく)に師事した。昭和初期には、国内最大の書道団体「泰東書道院」理事となり、書家としての地歩を固めた。
教科書や手本の揮毫・編集に携わったのは明治30年代からで、著作は100冊以上。大正期に全国の小学校で使われた国定教科書も手掛けた。
戦後は一般向けの文化書道会(東京)を立ち上げ、「実用の書家」というイメージが強いが、最晩年まで無鑑査の立場で日展や毎日書道展に「芸術の書」を発表し活躍。特別展では両展覧会に出品した12点を中心に据える。ほとんどが自作の漢詩が題材で、70代から最晩年までの作品を年代順に追うことで、無為自然に変化する「芸術性の進化」が確認できる。
林学芸員によれば、呉石が70代を迎えた1950年代初頭、作家の内面の感覚を熱く激しく表出するような抽象表現美術「アンフォルメル」が欧米で登場し、やがて日本の書壇にも影響を及ぼした。「前衛書にこそ芸術性がある」との考えが潮流となる中で、呉石は「磨き上げた技術の上に自然とにじみ出てくるものこそが個性」と考え、あえて「創り上げる」ことをしなかった。それが「前近代的」ととらえられ、歴史に埋没したと推察される。
価値観が大転換した書壇と一線を画し、呉石は日本の伝統的な芸術観を根底に据え、自己の目指す書を世に問い続けた。人格の修養と国語や漢文に習熟した広い教養から生み出された作品は、能楽などの伝統芸能の美にも通じる在り方だと林学芸員は解説する。呉石が長寿で生涯現役だったために到達できた世界でもある。2020年は呉石の没後50年にあたる。特別展を契機に、呉石の作品と芸術観を見つめ直し、勝山の偉人として未来に伝えたい。
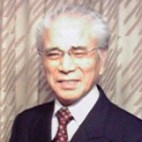
コメント